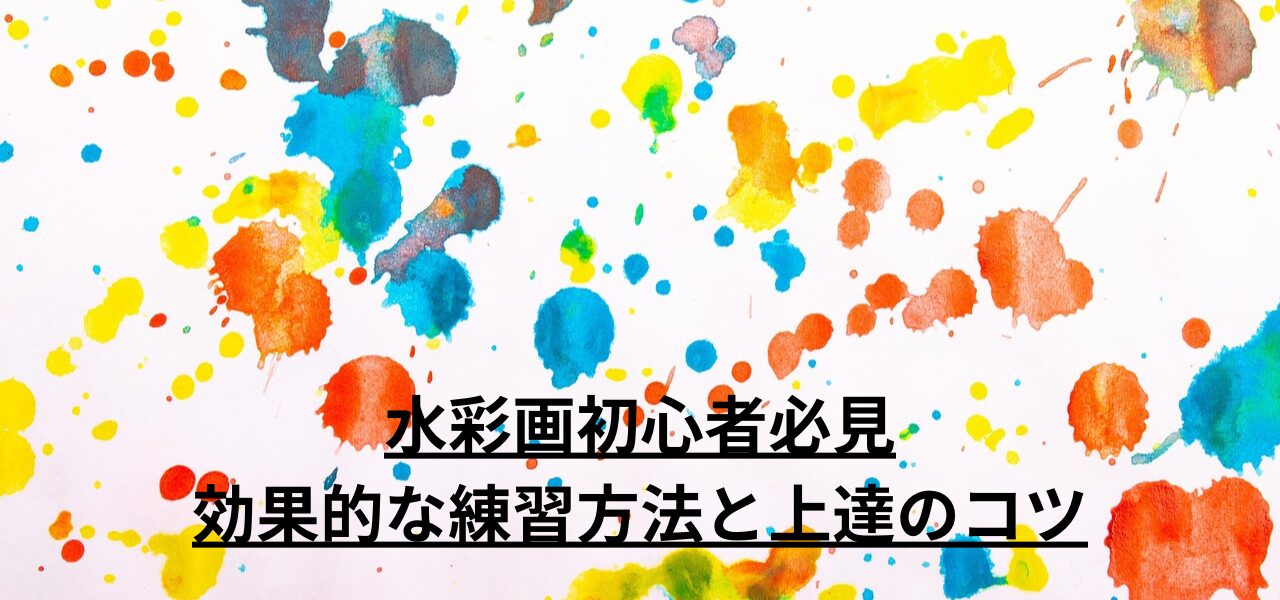水彩画は、柔らかな色彩や透明感のある表現が魅力の絵画技法です。
絵の道具と水が織りなす偶然のにじみやグラデーションが、独特の美しさを繰り広げます。
そのため、「これから水彩画を描いてみたい!」という方も多いでしょう。
しかし、いざ始めてみると、次のような悩みを恐れることはありません。
- 絵の具の濃さや水の加減が分からない
- にじみやぼかしが思った通りにならない
- 色を混ぜたら濁ってしまう
- 何から描けばいいのか分からない
この記事では、初心者が水彩画の基礎を学び、スムーズに上達できるよう、効果的な練習方法を詳しく解説していきます。
「絵心ないから無理かも…」と思っている方も大丈夫です。
大切なのは、少しずつ練習を大事にします。 まずは基本的なテクニックを学びながら、水彩画の楽しさを味わいましょう!
必要な道具を揃えよう

水彩画を始めるには、基本的な道具を揃えることが大切です。道具選びを間違えると、「思ったように描けない」「色が綺麗に発色しない」といった問題が起こることもあります。
水彩画を始めるのに必要な道具
まず、初心者が揃えるべき基本的な道具を一覧にしました。
| 道具 | 選ぶ側のポイント | 初心者向けおすすめ |
|---|---|---|
| 水彩絵の具 | 発色が良く、色移りしやすいもの | 固形水彩またはチューブタイプ |
| 筆 | 水含有が良く、滑らかなタッチのもの | 丸筆(中・小)+ 平筆 |
| 水彩紙 | 吸水性があり、にじみやぼかしがかなり軽いもの | コットン紙(中目~荒目) |
| パレット | 混色しやすい、洗いやすいもの | 白色のプラスチックパレット |
| 水入れ | 筆を洗うために2つあると便利 | 広口の容器2つ(汚れ用・きれいな水用) |
| ティッシュ・布 | 水分を調整するのに使う | 吸水性の高いもの |
| 鉛筆・消しゴム | 下書きするための道具 | H~2Bの鉛筆、練り消し |
各道具の詳しい選び方
水彩絵の具
水彩絵の具には「固形水彩」と「チューブタイプ」の2種類があります。
- 固形水彩(パンカラー):コンパクトで持ち運びが便利。初心者でも手軽に使えます。
- チューブタイプ:発色が良く、色が移りやすい。量を調整しやすく、本格的な絵に向いている。
初心者の方は固形水彩の12色セットから始めるのがおすすめです。
筆の選び方
水彩画では筆の種類とサイズ選びが重要です。
- 丸筆(中・小):曲線や細かい部分を描くのに適している。
- 平筆(大):広い範囲を塗るのに便利。
最初は丸筆(6号・10号)と平筆(大きめ1本)を揃えれば十分です。
水彩紙の選び方
水彩紙にはコットン紙とパルプ紙があります。
- コットン紙:水の吸収が良く、にじみやぼかしが綺麗に仕上がります。初心者でも使いやすい。
- パルプ紙:安価だが、水を含むと波打ちやすい。練習用には適している。
最初のうちはコットン紙(中目・厚手)を選ぶと、きれいな仕上がりになります。
初心者向けおすすめの道具セット
「何を買えば気にならない」という方は、以下のようなセットを揃えるのがおすすめです。
| 項目 | おすすめ |
|---|---|
| 水彩絵の具 | 固形水彩12色セット(ホルベイン、ウィンザー&ニュートンなど) |
| 筆 | 丸筆6号・10号、平筆(大) |
| 水彩紙 | コットン紙(アルビレオ水彩紙、アルシュなど) |
| パレット | プラスチック製のパレット |
| 水入れ | 2つの容器(100均でもOK) |
最初から高価な道具を揃える必要はありませんが、紙と筆はとにかく良いものを選んで、描きやすさが真剣に高まります。
水彩画の基本テクニックを学ぶ

水画を上達するために、基本的なテクニックを身につけることが大切です。 特に、水彩ならではの「にじみ」「ぼかし」「グラデーション」が上手く使えるようになると、表現の幅が一気に広がります。
グラデーションの練習
グラデーションとは、一色の濃淡を緩やかに変化させたり、異なる色を徐々に滲ませていく技法です。水彩画ならではの透明感を忘れた色の変化を表現できます。
基本的なグラデーションの作り方
- 筆にたっぷり水を含ませて、絵の道具を少しだけ取る。
- 紙の上に一番濃い部分を描きます。
- 水を足しながら、少しずつ色を薄めていきます。
- 筆を洗い、きれいな水で境界をぼかす。
【ポイント】
- 紙を少しずつ考えると、自然なグラデーションが作りやすい。
- 水をたくさん使うと、緩やかな色の変化ができます。
色を変えるグラデーション(カラーブレンド)
- Aの色(例:青)を塗ります。
- Aの色が乾く前に、Bの色(例:黄色)を次に塗ります。
- 筆を使って、目を覚ますようにぼかす。
こうすることで、自然に色が混ざり合い、美しい変化を繰り返します。
にじみやぼかしのコツ
水彩画の大きな特徴は、水を考慮したにじみやぼかしです。思い通りにじむには、水分量の調整が重要になります。
にじみの基本テクニック
- 紙を水で湿らせる(ウェットオンウェット技法)。
- そこに濃いめの絵の具を使える。
- じわっと広がるのを観察しながら調整する。
【ポイント】
- 水を塗りすぎると、広がりすぎてしまう。
- 乾く直前に色を入れると、にじみが柔らかくなります。
ぼかしの練習
ぼかしとは、色の境界を見極める技法です。
- 筆に水だけを含ませ、色の境界をなぞる。
- な軽くじめるように筆を動かします。
- 筆を洗い、水分を調整しながら仕上げます。
【ポイント】
- 乾いた状態ではぼかしにくいので、少し湿っている状態で行います。
- 筆の水分が多すぎると、逆に色が流れてしまうのでご注意ください。
ウェットオンウェットとウェットオンドライの違い
水彩画の塗り方には「ウェットオンウェット」と「ウェットオンドライ」という2つの基本技法があります。
| 技法 | 特徴 | 使い方の例 |
|---|---|---|
| ウェットウェット | 紙を濡らした状態で色を使える | 柔らかい背景、空、にじみの表現 |
| ウェットオンドライ | 乾いた紙に色を使える | はっきりした形、はっきりとした線を描く |
ウェットオンウェットの使い方
- 紙全体を筆で湿らせます。
- 絵の具を使えると、ふんわり広がります。
- 色を重ねながら、にじみの効果を楽しめます。
【メリット】
- 柔らかく自然な雰囲気を出せる。
- グラデーションが美しく出来ます。
【グリーン】
- コントロールが雄弁で、思った形にしにくい。
ウェットオンドライの使い方
- 紙が完全に乾いた状態で、筆に絵の具を使えることが含まれます。
- はっきりとした線や形を描きます。
- 輪郭を描き込み、輪郭を強調する。
【メリット】
- くっきりした表現ができる。
- 細かいディテールを描いたものに向いている。
【グリーン】
- にじみやぼかしの効果が出にくい。
基本を技術をつけることで、自由な表現が可能になります。
最初は思うようにいかないかもしれませんが、何度も練習することでコツを掴めるようになります。
線や形を描く練習
水彩画では、色にじみやグラデーションだけでなく、線や形のコントロールも重要な要素です。
特に、しっかりとした形を描く力を身につけると、モチーフを正確に捉え、構図を整えることができるようになります。
この章では、線を無視する練習と基本的な形を描く練習方法を解説します。
まっすぐな線と曲線を描く練習
水彩画では、筆の動きをコントロールすることが大切です。
まずは、まっすぐな線や曲線を練習して、筆を自由に扱えるようになりましょう。
直線を描く練習
- 筆に適量の水を含ませて、絵の具をなじませます。
- 軽い手首を動かしながら、一定の太さの線を優先。
- 筆圧を調整し、細い線と一時線を描く選択。
【ポイント】
- 筆を一気に進めるようになると、迷いのない線が引ける。
- 筆圧を変えてみると、表情のある線が描ける。
カーブやジグザグ線の練習
- 筆の角度を一定に保ちながら、ゆっくりとカーブを描きます。
- 同じ動きを何度も繰り返し、安定した線を示します。
- リズミカルに筆を動かしながら、ジグザグ線を描いてみる。
【ポイント】
- 筆を寝かせすぎると、思った通りのインフレになりにくい。
- 腕全体を動かすようにすると、スムーズなインフレが描ける。
基本の形を描く練習
水彩画で物を描くときには、基本的な形(円・四角・三角など)をしっかり描くことが大切です。これができるようになりますように、複雑なモチーフもバランスよく描けるようになります。
| 練習内容 | 目的 | ポイント |
|---|---|---|
| 円や楕円を描く | 形を取る | 軽く手を動かしながら平等な円を描く |
| 四角形・三角形を描く | 安全な構図を作る | 各辺の長さや角度に注意する |
| 影のついた立方体を描く | 立体感を学ぶ | 明暗を意識しながら塗装 |
円や楕円を描く練習
- 鉛筆でとりあえず下書きをする。
- 輪郭に沿って、筆でなぞるように描く。
- 筆圧を調整しながら、途切れないように線をつなぐ。
【ポイント】
- 楕円円は縦横の比率を意識すると、ゆがみにくい。
- 筆の水分量を一定にすることで、線の太さが安定する。
四角形や三角形を描く練習
- 四角形や三角形を鉛筆で下書きする。
- 辺を大胆に描くように、線のブレを防ぎます。
- 筆を軽く持ち、力を入れすぎないようにする。
【ポイント】
- 正確な輪郭を描くことで、構図のバランスが整う。
- 描画スピードを一定にすると、線が歪みにくい。
影や光の入れ方を学ぶ
モチーフに影や光を入れて、よりリアルな立体感を表現できます。
影の入れ方(明暗をつける)
- 光の方向を決める(例:右から光が当たる)。
- 影になる部分を薄く色付けします。
- 徐々に色を考えて、考えてみます。
【ポイント】
- 影の輪郭をぼかすと、自然なグラデーションができる。
- 光が当たる部分は放置しておくと、立体感が出る。
線や形の練習方法まとめ
ここまで紹介した基本的な線や形の練習を、継続的に行うことが重要です。以下のような練習メニューを取り入れて、無理なく上達できます。
| 練習内容 | 目的 | おすすめの頻度 |
|---|---|---|
| 直線・曲線を描く | 筆のコントロールを向上させる | 毎日5分 |
| 円や四角形を描く | 形のバランスを学ぶ | 3回 |
| 影のある立体を描く | 立体感をつける | 2回 |
【練習のポイント】
- 毎日少しずつでも続けることが大切です。
- 最初は形が崩れても気にせず、繰り返し練習する。
- 影を意識することで、よりリアルな表現ができるようになる。
水彩画の基本は、筆の動かし方や形の捉え方を練習することから始めます。
色の混ぜ方の基本

水彩画の魅力のひとつは、透明感のある美しい色合いです。
しかし、「色を混ぜたら濁ってしまう」「思ったような色にならない」という悩みを持つ初心者も多いでしょう。
この章では、色の混ぜ方の基本や進め方のコツを詳しく解説します。
三原色と色の基礎知識
水彩画の色を理解するために、まずは三原色(赤・青・黄)の仕組みを知っておきましょう。
| 色 | 役割 | 例 |
|---|---|---|
| 赤(マゼンタ) | 温かみのある色を作る | ピンク、オレンジ、紫 |
| 青(シアン) | 冷たい印象の色を作る | 水色、紫、緑 |
| 黄(イエロー) | 明るさを出す色 | オレンジ、緑、茶色 |
混色の基本ルール
- 赤 + 青 = 紫
- 青 + 黄 = 緑
- 赤 + 黄 = オレンジ
さらに、三原色を混ぜると茶色や黒に近い色になります。
【ポイント】
- 混ぜる色が多いほど濁りやすいので、2色までにする。
- 透明感を生かすために、水の量を調整します。
透明水彩ならではの色の作り方
水彩画の色作りでは、「色を混ぜる」だけでなく「初代」では新しい色を作る方法もあります。
パレットで混ぜる方法(ウェットミックス)
- パレットに2色の絵の具を出す。
- 筆で軽く混ぜて、新しい色を作ります。
- 水の量を調整しながら塗布。
【メリット】
- 色のコントロールがしやすい。
- 濁りにくい色を作れる。
紙の上で混ぜる方法(グレージング)
- 一色曇り塗り、乾かす。
- その上から別の色を。
- 透明感を大切にしながら、新しい色を作ります。
【メリット】
- 水彩ならではの透明感が出る。
- ヴィンテージのある色を表現できる。
【例】
- 黄色の上に青をと、きれいな緑ができる。
- ピンクの上に青を先ほどと、パープルな紫になります。
色を濁らせないコツ
「思ったよりも色がくすんでしまう…」という場合は
以下のポイントを意識するだけで、透明感のある美しい発色が得られます。
| 問題 | 原因 | 改善策 |
|---|---|---|
| 色が濁る | 混ぜすぎ | 2色までにする |
| 発色が悪い | 水分が多すぎる | 絵の具の量を調整する |
| くすんだ色になる | 反対色を混ぜている | 似た色同士を混ぜる |
色が濁らないための3つのルール
- 一度にたくさんの色を混ぜない(2色まで)。
- 先ほどの塗りときは、しっかり乾かす。
- 色の相性を考えて挑戦(反対色は反対)。
配色の基本ルール
絵の雰囲気を決める大切な要素が決まります。これからを意識すると、統一感のある美しい作品になります。
類似色を使う(いつかのある行事)
- 例:青・水色・緑(寒色系)、赤・オレンジ・黄色(暖色系)
- そこにあり、優しい印象になります。
補色を優れる(メリハリをつける)
- 例:青×オレンジ、赤×緑、黄×紫
- コントラストが強くなり、目が覚める絵になる。
明度・彩度を意識する(色のバランス)
- 明るい色(黄色、ピンク) → 軽やかで柔らかい印象
- 濃い色(青、茶色) → 落ち着いた雰囲気
【ポイント】
- 背景は薄めの色、主役ははっきりとした色にするとバランスが取れます。
- 全体に1~2色のメインカラーを決めると、統一感が出る。
色の練習方法
実際に色を使いこなすためには、今後を意識した練習をすることが大切です。
| 練習内容 | 目的 | ポイント |
|---|---|---|
| 三原色の混色 | 色の仕組みを理解する | 赤・青・黄の組み合わせを挑戦 |
| 補色の組み合わせ | 出会うことを学ぶ | 反対色を隣に塗ってみる |
| 薄い色と濃い色のグラデーション | 色の濃淡を調整する | 水の量を変えて塗る |
| 透明感のある色の重ね塗り | 水彩らしい表現を学ぶ | 乾かしてから2色塗布 |
おすすめの練習方法
- パレットで基本の色を混ぜる(三原色から緑・紫・オレンジを作る)。
- 色を試して、コントラストの補填を観察する。
- 紙の上で色を重ねて、透明感を活かした色作りをしています。
水彩画の魅力は、
色の組み合わせによってさまざまな表現ができることです。
最初は上手くいかなくても、繰り返し練習することで自分らしい色の使い方が見つかります。
簡単なモチーフを描いてみよう

ここまでの練習で、水彩画の基本的な技術(筆の動かし方、色の混ぜ方、にじみやグラデーションの使い方)を学びました。
初心者でも描きやすいモチーフとして、果物・花・風景などを取り上げます。
それぞれの描き方を、手順に沿って解説します。
基本的な描き方の手順
今後モチーフを描く場合でも、次の4つのステップを意識すると、スムーズに進められます。
| ステップ | 内容 | ポイント |
|---|---|---|
| ① 下書きをする | 鉛筆で形を薄くする | 消しゴムを使いすぎない |
| ② 明るい色から塗る | 一番明るい部分に継続色を使える | 水多めに使う |
| ③や影濃い色を | 立体感を出すために前の色を | 濃い色を少しずつ続ける |
| ④最後に思い出を調整する | ハイライトや細かい線を描く | メリハリをつける |
では、この手順を踏みながら、実際にモチーフを描いてみましょう!
初心者向けの簡単なモチーフ

①りんごを描いてみよう(基本の果物)
りんごはシンプルな形状と鮮やかな色で、水彩画の練習に最適なモチーフです。
手順
- 鉛筆で一時円を描き、りんごの形を決めます。
- 薄い黄色を全体に塗り、乾かす(下地)。
- 赤色を重ね、セキュリティを意識しながら装着。
- 光の当たる部分を軽く残し、グラデーションをつける。
- 影(青や紫を混ぜた色)を入れて立体感を出す。
- 最後にヘタを描き、細かい調整をします。
【ポイント】
- 最初に薄い黄色を塗ると、自然な色合いになります。
- 赤一色ではなく、オレンジや紫を少し混ぜてみると出る。
②チューリップを描いてみよう(シンプルな花)
花は形が単純なので、初心者でも挑戦しやすいモチーフです。
手順
- 花の輪郭を鉛筆で軽く描く(勇気のある花びら)。
- 花の部分に薄いピンク(または黄色)を描きました。
- 乾く前に、濃いピンク(またはオレンジ)を下の方に使える(グラデーション)。
- 茎と葉を緑で描く(濃淡をつける)。
- 花びらの影を薄い紫や青で加えて、立体感を出す。
【ポイント】
- 花びらの端をしばらく放置すると、光が見えるように見えます。
- 葉の色は緑1色ではなく、黄色や青を混ぜると自然に見えます。
③シンプルな風景を描いてみよう(空と山)
風景画は水彩画のにじみやグラデーションをわかりやすく、初心者におすすめです。
手順
- 空を描くため、紙全体を水で湿らせる(ウェットオンウェット)。
- 青色を上から塗り、下にいくほど継続してグラデーションを作ります。
- 山を薄い緑や青で描き、遠近感を出す(淡い色を奥に、濃い色を手前に)。
- 草や木を筆の先を使ってポンポンと描き足す。
- 最後に細かいディテールを加えて仕上げています。
【ポイント】
- 空のグラデーションは水をたっぷり使い、ムラなく広がる。
- 遠くのものはよく、近いものは眺めと光景が出る。
作品を仕上げるコツ
メリハリをつける
作品を魅力的に見せるには、明暗をはっきり付けることが重要です。
| 明るい部分 | 暗い部分 |
|---|---|
| 光が当たる場所 | 影や奥まった部分 |
| 色を豊富に、水をたくさん使って | 濃い色を重ねる |
【ポイント】
- 光が当たる部分は紙の白を活かす(塗らずに残す)。
- 暗い部分は青や紫を足すと自然な影になります。
細かいディテールを続ける
作品の完成度を上げるには、最後に細かい部分を整えることが大切です。
- 白抜き(ハイライト): ひたすら筆やティッシュで色選んで、光を表現する。
- スプラッター技法:筆を弾いて水滴を飛ばし、雨や霧の効果を出す。
- 筆の先を使って線を描く:花の茎や枝を細く筆で描くと、リアルな質感が出る。
【ポイント】
- 描きすぎないことも大事!最低限の線でシンプルに仕上げると、水彩らしい透明感が出る。
小さな作品をたくさん描こう!
水彩画は練習を忘れずに上達するので、最初は小さな作品をたくさん描いたものがおすすめです。
| 取り組み方 | いいね |
|---|---|
| 毎日1つの小さなモチーフを描く | とりあえず技術が身につく |
| 同じモチーフを何度も描く | 形や色がわかる |
| ないろいろ色の組み合わせを挑戦 | 偶然のセンスが磨かれる |
「上手に描こう」と思いすぎず、水彩の偶然のにじみや色の広がりを楽しんでみましょう!
まとめ
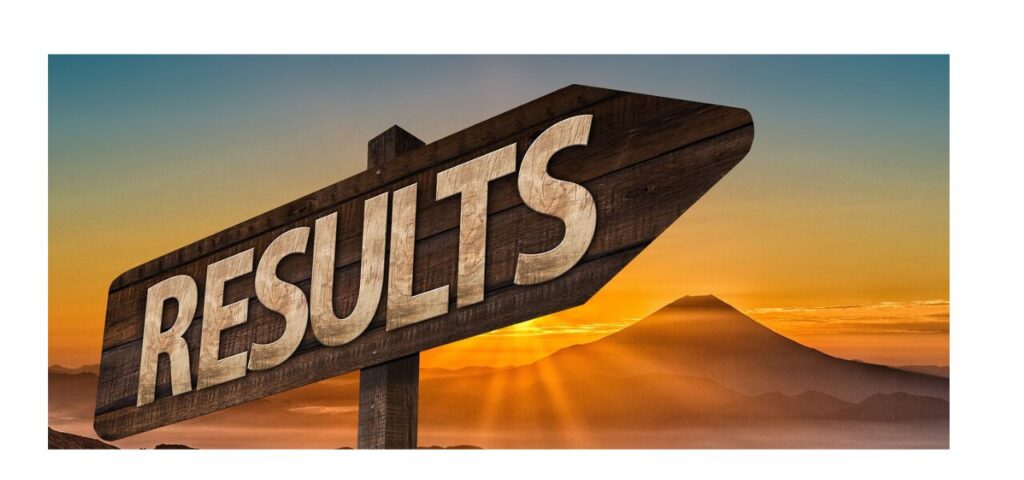
水彩画は、にじみや透明感のある美しい表現が魅力の絵画技法です。最初は思い通りに描けないこともありますが、基本を抑えて継続的に練習することで、誰でも確実に上達します。
この記事では、水彩画初心者が知っておくべき道具の選び方や基本技術、練習方法について詳しく解説しました。最後に、初心者が押さえるべきポイントを整理しましょう。
水彩画上達のためのポイント
① 道具選びは予想通り
- 紙は厚手のコットン紙がおすすめ(にじみがかなり薄い)。
- 筆は丸筆(6号・10号)+平筆(大)を用意しておくと便利です。
- 絵の道具は固形水彩かチューブタイプの12色セットが使いやすいです。
②基本技術をしっかり身につける
- グラデーションやにじみのコントロールを練習する。
- ウェットオンウェットとウェットオンドライを使い分ける。
- 線や形を正しく描くことで、モチーフをしっかり表現できる。
③色の混ぜ方を理解する
- 三原色(赤・青・黄)を活用して、色の組み合わせを学ぶ。
- 2色までの混色を意識すると、色が濁らない。
- グレージング(重ね塗り)を使うと、透明感のある色合いができます。
④実際にモチーフを描いてみる
- りんごやチューリップ、シンプルな風景からはじめます。
- 光と影を意識すると、立体感が出る。
- 筆の動きを観察しながら、少しずつ描き方を工夫する。
⑤継続が上達のカギ
- 短時間でもいいので、毎日筆を持つ習慣をつける。
- 目標を決めて練習すると、モチベーションが続きやすい。
- SNSやワークショップを活用すると、刺激をもらえます。
楽しみながら水彩画を続けよう!
水彩画の上達には時間がかかりますが、「楽しむこと」が一番大切です。
- 「失敗してもOK!」と思って気楽に描きました。
- 「偶然のにじみや色の広がりを楽しむ」という水彩の魅力を大切にしています。
- うまく描けなくても、「昨日よりちょっと上達した」と考えます。
何よりも、「描くことが楽しい!」という気持ちを大切にしましょう!